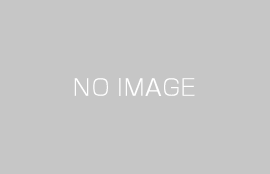※メッセージをお聴きになりたい方はこちら↓(音声のみです。再生中に、広告が入る場合があります。ご了承ください。投稿期間は約2カ月です。)
私たちはクリスチャンとしても、“体裁をかまう”傾向にあると思います。自分の信仰の歩みがどのように人に見られているかを重視してふるまう傾向です。自他共に、“人を見かけによって判断する”誘惑がある中で、神様は内面を重視され、外面は内面を忠実に映し出すものでなければならないことについて学びましょう。今回は以下の2ポイントを念頭に置きつつ学んでいきます。
① みことばに従うなら儀式は意味がある
② みことばに従うことは儀式以上に意味がある
パウロは、「あなたが律法を行うなら」と、継続的律法の実践に強調点を置いていますが(2:13)、実のところ誰も完璧に律法を行うことはできません。ただ完璧にではないにしても、基本的な実践が存在するのであれば、割礼のような外面的なことには価値があり、助けとなると言えるでしょう。割礼は最初アブラハムに命令されたことであり(創世記17:10~11)、それは神様との間の契約のしるしでした。割礼は、神様の民がこの世から聖別されることを象徴したのです。ユダヤ人は割礼を誇り、割礼を受けていない異邦人を軽蔑しました。割礼はそもそも、神様に対する従順の実践として、また神様との契約関係を思い出させるものとして意味があります。(ガラテヤ5:3)しかし、神様の律法を継続的に侵す(線を超える)ユダヤ人は、割礼を受けていない異邦人と同じ条件にあり、救いに関して特権を有してはいないのです。表面的(肉体的)なしるしは、内面の現実(内的きよさ)がなければ無意味だということです。
神様はクリスチャンである異邦人を、割礼を受けているクリスチャンであるユダヤ人と同じように好意的にご覧になられます。
律法を持たない(そして割礼を受けていない)異邦人の(律法に対する)謙虚で従順な姿は、(律法を持ち優位な立場にありながら)不従順の中で生きているユダヤ人への厳しい譴責となるのです。
28~29節でパウロは、なぜ割礼は救いを保証するものではないのか、そしてなぜ割礼の欠如が救いを妨げるものでないのかを説明しています。
適切に割礼を受けた、アブラハムの肉体的子孫が真のユダヤ人ではありません。神様は人種や宗教といった外的な事柄に左右されないお方であり、だれに対しても内的なきよさと誠実を求めておられるのです。「人目に隠れたユダヤ人」こそが、真の神様の子ども、真の霊的アブラハムの子孫なのです。(4:16; ガラテヤ3:29; ピリピ3:3; コロサイ2:11; 申命記10:16; 30:6; 使徒7:51; エレミヤ4:4; 9:26)表面的儀式が価値を認められるのは、人が、罪から神様へと分離した心の内面の現実を映し出す時のみです。(ローマ7:6; IIコリント3:6)救いは聖霊なる神様の(人の心における)働きの結果であって、単に律法に合わせようとする人の表面的努力の結果ではありません。ユダヤ人の名(呼称)は、“誉れ”を意味する“ユダ”から来ています。それゆえ真のユダヤ人は神様から来る誉れを受けるにふさわしい人であるということです。
まとめ:イエス様を信じイエス様に従う信仰生活の現実にこそ価値がある
今を生きるクリスチャンにとっては、割礼よりもバプテスマのほうがわかりやすいかもしれません。もしバプテスマを受けている事実が、“着ぐるみ”のようになっているのであればクリスチャンとしての価値はありません。大事なことはまことの神様との関係が健全なものであるかどうかです。神様との関係を土台としてなされるクリスチャンの歩みには価値があります。内面の(霊的)現実が存在するところに、表にあらわれる信仰の表現(バプテスマ、主の晩餐、礼拝出席、奉仕、献金など)が意味を持つことになります。イエス様を信じたかどうか、そして今信じているかどうか、そしてイエス様に対する信仰が生活で表現されているかどうかが重要なのです。(Iコリント7:19; ガラテヤ6:15; ローマ3:20)